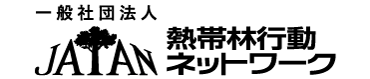フォトジャーナリスト 内田道雄
日本からほぼ南の赤道を超えた彼方に、世界で2番目に大きいニューギニア島がある。日本の約2倍の面積があり、西側はインドネシア領。東側はパプアニューギニア国(以下PNGと表記)となっている。
PNGの国土面積は4,631万ha。(日本の約1.2倍)ニューギニア島の東側と周辺の島々からなる。気候は全体に熱帯雨林気候だが、内陸は高山気候である。人口は約1,014万人。(2022年、世界銀行調べによる)
森林消失
昔はこの地域全域が、森林地帯であったと考えられる。戦後商業伐採により森林消失が始まった。紙の原料用に原生林を伐採したこともあった。
森林林業統計要覧によると、2020年の森林率は79.2%。2015年は72.5%だったので若干増えている。これは植林によると思われる。ただ、年変化は32,300haの減少となっている。数字が矛盾しているが、森林地帯の状況は明確にはわからないのだろう。
1990年代の丸太輸出は約200万㎥でそのうち7割近くが日本向けだった。その後、丸太の生産量は、2008年に857万㎥で‘10年に1,000万㎥となった。そして‘15年まで毎年900万㎥以上を生産している。最近のデータでは2017年から‘22年まで960万5000㎥で変化がない。おそらくきちんとした統計が得られないと考えられる。
2019年のPNGの全丸太輸出は375万㎥。そのうち87%が中国向けだ。日本の輸入量は10万㎥ほどだ。だが‘18年のPNGからの丸太輸入は7万6394㎥でそれより増えている。
パプアニューギニアの森林消失の原因は商業伐採やプランテーション開発が48.2%。焼き畑耕作で45.2%。人口増加により焼き畑も持続可能にできない、という研究もある。
私はこれまで数回PNGを訪れた。今年の2月には森林伐採が終わった地域を訪れた。森林伐採は地域の人々に様々な影響を与えている。人々は伐採が終わった後の生活の激変にもめげず、新しい環境に適応することに挑戦していた。

アブラヤシ農園を模索する
ニューギニア島北部の東セピック州にトゥルブといわれる地域がある。州都である沿岸のウエワクから幹線道路が通り、いくつかの村が点在している。この地域の森林伐採はもう終わっている。私がこの地域を初めて訪れたのは2018年だが、その頃はまだ伐採は行われていた。森林資源の枯渇や地元住民の反対運動で現在では森林伐採は行われていないという。
だが、この地域にはアブラヤシ農園開発が行われている。
アブラヤシからはパーム油が採れる。現在世界で最も生産されている植物油だ。食品が主だが、様々な製品に加工され私たちの身の回りに存在している。
アブラヤシは熱帯でしか栽培できない。生産のほとんどはインドネシアとマレーシアだがニューギニア島でも生産されている。
パプアニューギニアのアブラヤシ開発は50年ほど前から行われている。歴史は古いが、現在でもパーム油の生産量は50万トンほどしかない。プランテーションでのパーム油生産量は、1ヘクタールあたり4トンほどである。したがって栽培面積は10数万haと推定される。だがパーム油の需要は増えているので、今後は生産量が増加して行くことが予想される。
土地所有制度について
パプアニューギニアでは国土の97パーセントがいわゆる慣習地である。この土地は住民に所有権があるが、氏族や地域コミュニティーなどの集団所有となっている。個人で所有権は持てない。伝統的に使われてきた土地なので、境界などははっきりしていないことが多いという。
1979年の土地法で「特別農業 事業リース」:SABL(Special Agricultural and Business Lease)というシステムが導入された。これは土地所有者がいったん国に土地をリースして、それを国が利用者にまた貸しする。最長で99年間設定できる。このシステムはリースといっても賃借料などははっきりしていない。地主の取り分がいくらなのかなど、きちんとした約束がないこともある。
また、土地をリースするには地主たちの同意がいる。しかし、地主のなかの一部からのみ同意を取っているだけなのに、全体が同意しているような同意書の偽造が横行していた。地主のなかの有力者だけに賄賂を渡して、全体の合意を取ってしまうことなどもある。
2003年から‘10年に国土の10%に当たる、420万haにSABLが設定された。この方式に関しては様々な問題が指摘されている。
アブラヤシプランテーションを作る場合、企業はSABLシステムにより土地を確保する。しかし企業の中には森林を開発する許可を取ったとしても、木材の伐採のみ行い油ヤシ栽培をしないこともある。これはアブラヤシ農園開発の利益ではなく、材木の販売のみを狙ったものだと考えられる。
アブラヤシ農園の影響を受けているサマウエア村を訪れた。ここには2つの集落があり108軒、600人ほどが暮らす大きな村だ。自給的農業が主だが、カカオ、バニラ、バルサ材など換金作物も栽培している。
村人の話によると、2009年に伐採が来た。村の土地が伐採されたが特に補償などは無かった。丸太を少量もらっただけだ。私はPNGでは地元住民に土地権があるのになぜ補償がもらえないのか不思議に思った。だが村人は私に何で補償がもらえるのかを逆に聞いてきたのだ。どうやら土地権があっても木材の所有権は無いようなのだ。また自然に生えている木がお金になるとは考えていないようだ。結局住民は伐採による保障はほとんど得てはいない。

伐採が終わった後にアブラヤシ農園開発が始まった。2011年に植えられたが、近くに搾油工場が無いという。もう15年も経っているので、アブラヤシは十分に育っているが収穫は行われていない。現場に行ってみると農園は草に覆われている。アブラヤシの木もつる草が生い茂り枯れてしまったものもある。私は5年ほど前にもここを訪れたがその時よりひどくなっていた。このままではこの農園は完全に使えなくなってしまうだろう。どうやら企業は森林伐採の木材だけが目的で、アブラヤシ農園は経営する気は無かったようだ。
村の人たちは何とか自分たちで運営できないかを考えている。しかし搾油工場を作って操業するのはかなりの専門知識と技術が必要だ。とても村人だけでできるものではない。本来なら政府がきちんとした対応をすべきだが、PNGの政府は地方の住民にあまり関心が無いように見受けられる。この地域も町から車でほんの数時間の距離なのに伝統的な暮らしからほとんど変わっていない。電線や水道も無く、今が21世紀と思えないような生活だ。
この農園のSABLは2017年に取り消されたという。何とかアブラヤシを住民が生産できるようにしてもらいたいものである。
カカオ農園計画
また、この地区のタマサウ村ではカカオ農園を作ろうとしている。村の土地であった伐採跡地には大きな木はもうないので農園を開くことは難しくないようだ。
この村では試験的にカカオの栽培を始めている。見たところまだ木は小さくて生産量もないが今後は大規模にやっていきたいという。
その後村の近くの森に行ってみると、原生林に近い森林が残っていた。直径1メートル以上の巨木や、つる植物が寄生されて空洞になった巨木もある。このような森は残してもらいたいものだが、村人はここも開発したいと考えている。何とか森を残しながら生活できる方法を考えてもらいたいものである。

保護区の制定
私が東セピック州を訪れたのは現地のNGOを紹介されたからだ。そのNGOは代表の方が亡くなったため現在活動停止中だ。だがメンバーの方の息子さんが自然保護区の管理に尽力している。
代表のユージンさんによると、この地域は1978年にモジィラウ自然保護区という名で国に指定されているが、特に整備はされていなかったという。保護区の中でも森林伐採が行われている。現在7,300haの森林管理を行っている。今後は保護区を広げていきたいと考えている。またエコツアーなども行っていきたいということだ。

たまたま今回訪れた時、管理事務所のオープニングセレモニーがあると聞いて見学した。昨年も現場は訪れたがその時は建物が一つだけだった。今回は3つの建物があり、大きなホールも建築中だ。明日開会なのに大丈夫かと思ったが何とかなるという。当日は近隣の住民が数百人も集まり、伝統的な踊りも行われお祭りのような盛大な式典になった。地域の行政機関の人も来て、正式に政府に認められていることがよく分かった。
まだ始まったばかりのプロジェクトだが、破壊された森林の回復や保護に成果の上がることを望むものである。

(了)
※この記事はJATAN News No.123からの転載です。
【参考】
内田道雄「破壊が続くパプアニューギニアの森林」(JATAN News No.114)
内田道雄「パプアニューギニアのアブラヤシ農園を訪ねる」(JATAN News No.115)
内田道雄「パプアニューギニアの森林伐採地を訪ねて」(JATAN News No.120)